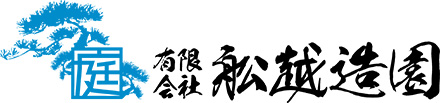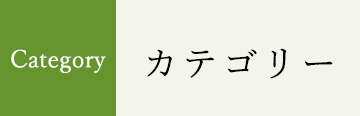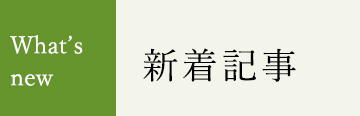2021年06月25日
カーポート裏のフェンスが剥き出しになっている場所に生垣を植栽するご要望をいただきました。
当社は浜松市北区に会社がありますが、アクセスさえ良ければ天竜区でも作業にお伺いすることが可能です。目安としては自動車で片道1時間程度でしょうか。
もし庭造りや庭リフォームをお考えの方で「こんな遠くまで来てもらえないだろうな・・・」とお思いの方がいらっしゃいましたら、一度お問い合わせください。
カーポートの後ろは隣地の公共施設が目につきます。
一部、コンクリート平板が設置されている区間もあり、なかなか素人の方の装備では難しいと感じました。
周辺を多少試掘してみて、それほど難儀な事は無さそうだな手応えを感じたので、そこは見積もりに反映させます。
生垣の新設とは別に、既存の植栽が樹勢が悪く診てほしいとのご依頼を受けましたので確認したところ、明らかに根っこの状態が良くないのではないかというサインをいくつか見つけましたので、一度掘り上げて土壌改良した上で植え直し、発根を促すような環境に変えるご提案をさせていただきました。

そして、こちらの御施主様宅には立派なサクラの木があるのですが、よく見ると「てんぐ巣病」に罹患している枝がチラホラ見受けられます。

写真中央、下段の幹の股部分や中央上の方に、モジャモジャと通常より多めに細かい枝が出ているのが見えますでしょうか?
これはお施主様がご自身で発見されてご心配されていたので、まだごくごく初期の段階ではあるのですが、工事の際に一緒に病枝を切除してしまいましょう、とご提案させていただきました。
てんぐ巣病とは、枝葉が異常なまでに細かく出てしまう病気の一種で、モジャモジャとした細かい枝葉が比較的高いところに発病することから、この名がついたとも言われています。
放っておくと全体に転移し、枝をスカスカのスポンジ状にしてしまい、最終的には枯らしてしまいます。
まずはベテランの職人に先乗りしてもらって、てんぐ巣病の枝を徹底的に切除してもらいました。葉っぱが載っているときにはなかなか発見するのは難しいのですが、そこは年季の入ったベテラン職人です。「取り切ったはずだよ」と白い巨塔の財前教授もかくやという頼もしい言葉をもらいまして(性格は財前教授とは全く違う誠実な人です・念のため)後顧の憂いなく植栽作業に進んでいけます。
2021年06月18日
倉庫の裏にあるデッドスペースをキレイに整備できないかというご依頼をいただきました。
写真には写っていませんが、すぐ横には畑があるので、畑仕事の休憩に使ったり、ちょっとした集まり(お茶会とかバーベキューとか?)に使ったり、構想は広がります。実はこの段階が一番楽しいのかもしれませんね(笑)

とりあえずボサボサになっていたスペースを草刈り&樹木剪定を行い、全容の見える状態にしました。朽ちそうに見える小屋の様なものも趣があっていいですね!茶道でいうところの待合のような感じに使えるかもしれませんが、とりあえずこのスペースは保留という事で、その他の広いスペースをキレイな庭にして、ローメンテナンスを実現させることを主眼に置き、進めていきます。

バックホウ(ショベルカー)を使って雑草の根や不要な樹木の根も掘り取っていきます。この段階でしっかり根っこの処理をしておかないと、後々どこからともなく伸びてくる量が多くなりすぎてしまって、全く取り返しがつかなくなってしまいますので、時間をかけて作業します。

きっちりと下地を作ることができました。

その次は防草シートと砂利敷きを行います。
防草シートは予算の関係もあり、簡易的な薄手のシートを採用しました。
当社ではこのシートといかな雑草にも負けないと触れ込みのザバーンの2種類を採用しています。
簡易シートは確かに強度も弱いですし、放っておけば劣化も早いのですが、シートの上に砂利を敷く条件下であれば紫外線による劣化も問題ないので、こちらの経済的なシートをお勧めする様にしています。
このほか、様々な制約もあったりしますので、詳細は現場ごとにお伝えできればと思います。
とにかく、今回の現場ではこちらの簡易シートでも問題ないという結論です。

切り株を残してあるのは、切り株の脇から芽を出させて新たな雰囲気の庭木として生まれ変わらせようという試みです。
ズドーン!と太い幹が高く伸びる庭木から、根本で何本か細い幹が伸びる株立ちのような雰囲気を持たせようとしています。
完成までに数年かかるかと思いますが、そこは自然の生き物ですので、待っていただき、年々成長していく樹木を時折見ては「おっ!?」となるのもまたオツなのではないでしょうか。

また、しばらく手をつけていないスペースをしっかり整地すると思わぬ問題点が解消したりします。
何だかジメジメしているなぁ、こんなはずじゃないんだけどなぁ、と不思議に感じていたところ、何と排水がうまくいっていなかった問題点を発見しました。
倉庫の屋根に降った雨水が雨樋を通って雨水パイプに入るのですが、肝心の地上部分が地下へと続く部品とジョイントされておらず、ボサボサの枝の干渉などによって、上手く地中へ雨水が入っていなかったんですね。様々な思惑もあって地中部と地上部のジョイントはしていなかったんでしょう。この構造はこのままおくとして、パイプの周辺は防草シートと砂利で覆ってしまうので、これ以降、枝が干渉する様な事はないと言えるでしょう。これで、ジメジメも軽減されるかと思います。
残した植栽の周りには小石で砂利留めを行い、地被類を植えて庭のバランスを整えます。
元々このエリアにはツワブキが大量に生えていましたので、それを再利用しない手はありません。
ツワブキは草の類にしては幅も高さも強調することができ、丸い葉っぱも印象的な本当に使い勝手の良い植物です。
和風によりすぎてしまうのは難点と言えば難点ですが、他に組み合わせる植物次第で様々なカテゴリーの庭に植栽できると思います。
日陰にも強いので、うちの庭は日陰で・・・とお悩みの方は、ぜひ使ってみてください。

再利用といえば、こちらの側溝ふた。これも現場に大量に余っていたものですが、庭エリアと倉庫の表側を繋ぐための通路を歩きやすく汚れにくくするために再利用しました。
これだけの通路面積をオシャレなアンティークレンガで作ろうと思ったら、まあ予算がいくらあっても足りません。側溝のふたといえど、歩きやすさや足元の汚れなさは抜群に良いのです。庭のメインエリアからは外れているので、まあこういう通路もご愛嬌ということで。
畑と庭は実は段差があって間知ブロックで仕切られているのですが、長年の使用によって埋め立てられ、畑と庭がほぼフラットな高さになっている部分もあります。そこに、鉄平石という薄い石をモルタルで据えてその左右をしがらみで通れない様にし「入口出口はここですよ」と暗黙のうちに利用者に伝えるエリアを作りました。
間知ブロックの一番上はコンクリートとモルタルでまっ平に仕上げてあるので,その上に石を置いても高さが出過ぎてしまいがちなのですが、鉄平石は薄いものもありますので、違和感なくモルタルの天端の上に据えることができます。
また,竹をしならせて作る「しがらみ」も、近くにある竹林と相待って良い雰囲気を作ってくれています。
(ちなみに世間のしがらみなど、がんじがらめの人間関係を表すしがらみという言葉の語源でもあります。写真を見ると確かに、振り解きにくい形状をしています・笑)

もう一箇所、庭から畑へ、畑から庭へと移動する階段をつくりました。
細かい仕事をしても全く生きてこない広大なスペースの一角ですので、逆にあえて、現場にあった石ころと木の杭、番線などを使って無骨に仕上げてみました。
思ったよりも良い味が出ているんじゃないかなと感じます。

これにて、人が集まることを意識した、ローメンテナンスの畑横の庭、完成です。
今現在、コロナ禍によってなかなか活かせないのかもしれませんが、いつかきっと、畑仕事の休憩に皆で笑いながら楽しんでいただけることを信じています。
2021年06月11日
今回はちょっと変わった庭リフォームの現場をご紹介します。

昔に作られた土留めは間知ブロック(けんちぶろっく)を積み上げた、道路脇にあるごくありふれたものでした。
お客様はこの見た目をなんとかしたい。ついでに庭木の整理を行いたい。ただ、残したい木はあるのでそれは残したい。というオーダーを頂きまして、ここ最近当社で扱っている石材をふんだんに使った土留に変更する案をご提案しました。

早速パースを作成し、見積書と一緒にお持ちしたところ一発でご快諾いただきまして、早速仕事に着手することとなりました。

まずは間知ブロックを取り除きます。
実はこのブロック、地味に奥行きのある形状をしていて、ナメてかかるととんでもない失敗をするのですが、今回は重機がしっかり投入できる現場でしたので、ゴリゴリとブロックを取り除いていきました。
一番大きい白っぽい幹の木はモチノキで、この木の根っこの張り方も想像した通り。難しい埋設パイプなんかもなく、とりあえず一安心しました。

石積みのスタートとゴールの角は山石と呼ばれる地元産出の石を使います。石積みに使う石は大きなものはなく、片手で持てるくらいのサイズなので、カチャカチャと積んでいくには良いのですが、一番端の強度に不安が残ります。そこで、端っこだけは山石を使ってみることにしました。
これはこれで味のある庭になりそうで良かったです。

そうしたらドンドン石を積んでいきます。

ドンドンドンドン積んでいきます。

ここまできたら、あとは最後の天端(てんば)を残すのみ。
最後は石の頂上が全部一直線に揃わないといけないので、なかなか時間のかかる作業になります。

そして、天端の石を積み上げたら・・・完成です。
この石の表情、和風にも洋風にも、何にでも合いますね。アーリーアメリカンも演出できるんじゃないでしょうか?
ターシャの庭とかお好きな方は、ぜひお問い合わせください。
楽しいものをお作りできると思います!
2021年06月11日
大物を植えた通り庭、いよいよ仕上げ作業です。

現場から打ち合わせ要請。行ってみると、竹垣根で少しトラブル発生の模様です。
縦に立てる竹(立子たてこ)がコンクリートに乗ってしまうんだけど、しっかり結束するし、このままで大丈夫か?という相談でした。
もちろん答えはノー(笑)
良いわきゃないでしょ・・・
本来であれば杭の位置をバックさせて、このままの状態で竹垣根を作りたいところなんですが・・・実は土の中は様々な構造物のオンパレードでして、配管やコンクリート基礎など、全く杭を動かすことができない状況でした。(まあそれもあって、この状態でいいかという相談だったのですが)

本意ではありませんが、「どちらが良いか?」と言う選択肢を思い浮かべて、横に渡す竹(胴縁どうぶち)を杭の裏側に変更し、杭と胴縁の接点が目立たないよう接点に立子を立て、胴縁を後ろに回したことでできたコンクリートとの隙間に入るギリギリのサイズの竹を入れました。これで違和感は緩和されると思います。
「いやいや、コンクリートに乗せてもよかったんじゃないの?」というご意見もあるかと思いますが、これは感覚の問題ではなく明確な理由があるんですね。

完成後の写真を見ていただければ分かると思います。
竹垣根の根本、立子が土に埋まっている部分には地被植物(リュウノヒゲ)が植えてあるのがお分かりいただけると思います。
コンクリートの冷たい印象から和風の庭へと急に変化するこのエリアは、ガラッと変わってしまうこの境界線のコントラストをどう緩和させるか?がポイントになっています。
そこで、このようにリュウノヒゲという地被植物にしては比較的ボリュームのある植物を植えて緑のベルトを設けることで、コンクリートから和風庭園へ突然変化してしまうのを緩和させているんです。緩衝帯という考え方です。
ここに、剥き出しの竹がコンクリートに乗ってしまっていたら・・・せっかくの緑の緩衝帯も、その効果が半減どころかひょっとしたら効果そのものがなくなってしまうのかもしれません。
仕上げに向かう理想の前提条件が崩れたとしても(この時は地下埋設物の障害でした)今現在の状況で「お施主さまの心の安らぎ」を最大限表現するにはどうしたらいいのか?という事に心を砕いて作庭にあたるのが、施工者の誠意じゃないかなと強く感じています。
とかく、職人は手戻りを嫌うものです。せっかく作った仕事を台無しにされたくはないというのが本音です。
そこで、イヤイヤ待てと、それじゃあダメだと言える設計者がきちんといる事で、なし崩しに庭が作られていって、お客様が「こんなはずじゃ・・・」となってしまうのを防いでいるのです。
2021年05月19日
玄関前付近の庭を今回は報告します。

簡易トイレが据えてあるこのエリアに、敷地の奥へと入っていける通路兼坪庭を作庭していきます。
ポイントになるのは、1年前に苦労して掘り上げた大きなイヌマキです。これを、この庭で使用することが、お施主様の要望になりますので、イヌマキのサイズにしては植え込む庭スペースが狭いのでとても難しいのですが、しっかりと納めて、なおかつ庭として自然な感じに仕上げられればと思います。

まずは職人と構想のすり合わせです。最近ではiPadなど気軽に写真にドローイングできる機械が(機械てw)あるので、私の中にある構想を共有するのがとっても楽になりました。「舩越さんにお任せする」と言われた場合は、共有するための何がしかの絵は書くのですが、緻密な図面も作りませんし、現場の状況でどんどんアレンジしていくのが通常なので、こういう現場での職人とのすり合わせは欠かせません。
さあ、いよいよ大物の植え込み開始です。
元々「門かぶり」という1本の枝が門のように通路にかぶさっている仕立てのイヌマキでしたので、この細い通路でどう使うか、かなり悩みました。何とか枝を活かしたかったのですが、物理的なサイズを無視することは魔法でも使えない限りできません。何とか家の中からは枝振りを鑑賞できる雰囲気に持って行ける場所に据えることができました。
掃き出し窓のような目立つ場所ではありませんが、窓を開けるとイヌマキの枝が見える趣向になっています。
植え込みは、極力高く植えるようにしました。なぜかというと、奥に向かっていく通路のスペースはしっかり確保しなければならず、そのためには枝ぶりが邪魔になるからなんですね。これも限られたスペースで限界ギリギリ、何とか導線を確保することができたかと思います。
奥へと向かっていく飛び石と垣根の配置です。「飛び石」とは、平らな面を持つ石を連続して据え、その上をぴょんぴょん飛ぶように歩いていく日本庭園ではポピュラーな通路になります。
足の地面に接する部分を通行人に選んでもらうのではなく、作庭する側が「ここを踏んで歩いてください」と指定するんですね。なかなかこんな考え方の通路は無いかもしれません。
もっとも、そうやって足を踏みしめる場所を指定するからには、どうやって石を配置するかはとても重要な決定事項になります。広すぎてもダメ、狭すぎてもダメ。人は右足左足と幅がありますので、真っ直ぐ石を配置しても歩きにくい。使う人のシチュエーションも考慮しつつ、配置していきます。この辺、職人の腕の見せ所なんですね。庭を設計した者の意図を汲んで、与えられた材料で最高の仕上げに着地させる。なかなか一朝一夕にできる事ではありません。造園を行う職人としてセンスがあるか?それとも庭造りはちょっと難しいかなと思われてしまうか?庭造りを学びたい若手にとっては、プレッシャーな仕事になるんじゃないかなと思います。
これで色々と難しい場面は乗り越えました。次回は、いよいよこの坪庭の仕上げに入っていきたいと思います。