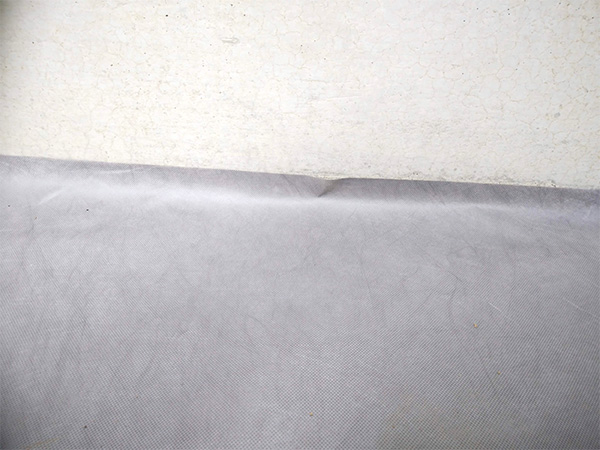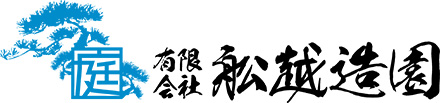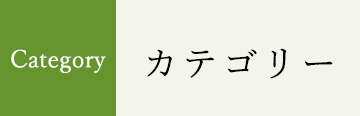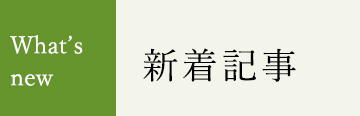2021年05月11日
大きな構造物が据え終わったら、地面の植栽や砂利敷きなどを行なっていきます。
玄関側から見ると、この坪庭はかなり低い位置にあるので、玄関に立った時には地面は見えない状態です。
ですので、実際に家に上がって部屋へ通されるその一瞬、お客様が目をやれば庭の地面が見える状態になりますからあまり奇抜にせずあっさりと仕上げようと思いました。


まずは地割り。タマリュウという地被類と砂利敷の境目を描きます。
ここで庭の大部分が決まると言っても過言ではないので、慎重にかつ大胆に?決めていきます。その際、作庭を担当している職人とも話したりします。

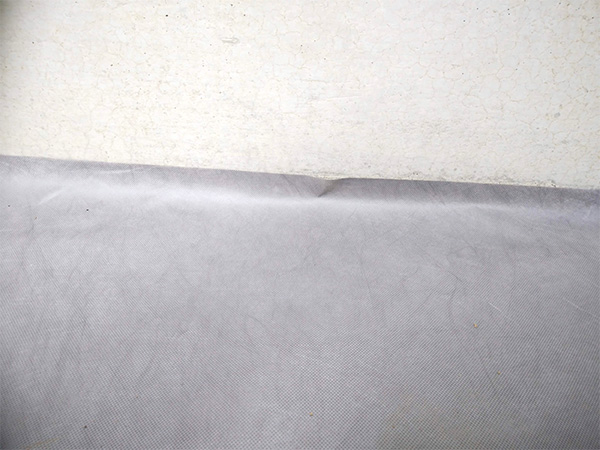
次に砂利敷きエリアに雑草を防止する棒草シートを貼っていきます。
特に隅の方は念入りに。裾を立ち上げるくらいの余裕を持たせて施工しています。
目に見えない部分なので、あっさり仕上げようと思えば簡単な話なのでしょうけれど、目に見えない部分だからこそ、何かの拍子にお施主様に見えてしまった時の印象が違うと思うのです。手は抜けません。


タマリュウと白川砂利のコントラストが美しい、とっても分かりやすい和風の坪庭、これにて完成です。
垣根から奥、裏の部分はもう少し手間が加わるので砂利敷きは一旦保留してあります。
立木は元々お施主様のお宅に植えてあったサザンカです。
木に関しては一年前に掘り取って会社の畑に仮植えしてあったものをしっかり使って作庭しました。
玄関をガラリと開けると、手前の大津垣と奥の大和塀が交差するように見え、隣家の駐車場を目隠ししつつ、奥行き感を出します。
玄関を上がってふと坪庭に目を落とすと、砂利とタマリュウの坪庭。
植栽が育ちにくい環境につき、サザンカの育成も少し不安なのですが、そこは毎日の水やりを欠かさず行なっていただくとして、比較的メンテナンスのしやすい庭に仕上げることができました。
住宅の雰囲気とぴったり合わせることができたんじゃないかと思います。
とかくこういうシチュエーションの坪庭は奇抜さを狙ってしまいがちですが、ストレートに表現できたのも、お施主様のご要望を汲みつつ作業できたことが大きいんじゃないかと感じています。
やはり、こういう庭造りは、どこかのハウスメーカーの下請けでは味わえない仕事なのかなと思いますし、20年前に「メーカーの下請けに回って作庭数を伸ばすか?」「作庭数は少ないけれどお施主様直接注文にこだわってきめ細かく作庭するか?」の選択を迫られた時に選んだ道は間違っていなかったのかもなと思います。
もっとも、建築会社様のご紹介で直接庭づくりをさせていただくという機会も結構あるので、もしご覧の建築会社様がいらっしゃれば、ご相談ください。
次は玄関前エリアの作庭に移っていきます。
2021年04月26日
さあ、建築も終了しまして一年越しに造園工事の再開となりました。

土間コンクリートや金物のフェンスなどは建築の方が手配されていまして、今回は当社での出番は無し。もちろん、様々なお付き合いなどありますし、お客さまであるお施主さんが信頼されている方に仕事をおまかせされるのが一番だと私も強く感じています。
もっとも、土間コンクリートや金物フェンスが苦手だからという訳ではなく、むしろ当社では専門職の方と一緒に仕事をしているので、年季の入った仕上がりにする事が可能です。ただ、先程のような理由もありますので、植木や庭石、竹を使った工作物など坪庭スペースのオーダーだけでもご満足頂けるものにするよう心がけています。
今回は、こちらの坪庭スペースです。

玄関を開けると最初に飛び込んでくる、まさにご自宅の顔になるスペース。
どのように表現していくか楽しみな場所でした。
奥行きはあまりなく、しかも隣家の生活感が見えてしまうスペースですので、目隠し効果を狙いながら奥行きのなさを感じさせないレイアウトを考えました。

まずは(玄関側から見て)奥の部分に垣根を建てます。渋いスペースにしたかったのと、行き着くにも狭いスペースを通るのでメンテナンスの頻度を下げたかったこともあり、奥の垣根は板塀としました。

焼いた板と晒し竹という材料を交互にリズムよくつけていく塀で、一般的に大和塀と呼んでいます。

手前側には塩化ビニール製ではありますが、大津垣という竹を編んだような垣根を設置しました。
見た目にもちょっと珍しいので目をひきますから、玄関に入ってきたお客様の視線をまずは坪庭に向かわせる効果を出すことができ、いきなり生活感が視界に飛び込んでこないような仕掛けにしています。

手前にある大津垣と奥に見える大和塀を違い違いに設置することで、感じにくい奥行きを少しでも感じられるようにしました。
からくりは、たがい違いになった垣根と塀の隙間が一定スペース空いたまま視界から消えることで、見たものがその先を想像し、より実際は無いスペースを感じ取ってもらうという仕掛けです。
大きな構造物はここまでになります。
次回はいよいよこの庭の仕上げ作業に入っていきます。
2021年04月12日
前回、庭木を掘るには、なかなか骨が折れるぞと覚悟を決めて移植作業に取り掛からなければいけないぞと言いました現場、いよいよ実際に庭木を掘り取ります。
建物の奥にある庭木から。
こちらは重機の入る隙間もなく、人1人が横向きになってようやく通れる隙間しかないので全て人力のみでの掘り取りです。
長らく庭に定着していた庭木ですので、細かい根っこがまんべんなく残っているわけもなく、ズン!ズン!と太い根っこを強引に切断して掘り取っていくしかありません。
太い根っこというのは、木全体の養分吸収の大部分を支えている場合が多いので、このままでは枯れてしまう可能性が高いです。
そこで、養分吸収を行う根っこの量とバランスをとるように地上部である枝葉の量も剪定によって減らします。
太い根っこがあってそれを切ってしまった場合は、その根っこに水分や養分の吸収量の大半を依存している可能性も高いので、より多くの枝葉を切除する必要が出てきます。
これでもか!というくらいに枝葉の剪定を行いました。

掘り上げた植木です。
根っこがきれいな円になっておらず、いびつな輪郭をしているのは、太い根っこに水分や養分の吸収を頼っている証。何とか根付かせたいですね・・・

すっかり掘り取りも終わって何だか広く感じる裏庭です。
ここで様々な家族ドラマが繰り広げられたのでしょうねぇ・・・などと感慨に浸っている場合ではありません。庭木を持ち出す通路も非常に細かったのですが、幸か不幸か根っこの状態も良くなくて大きな根鉢ではなかったので、何とか人力で持ち出すことができました。

懸案だった玄関前の大きなイヌマキの木ですが、どうせ解体するならとお施主様の承諾を得て、キツキツに植わっていた場所の縁ブロックごと破壊して庭木を取り出すことができました。このブロックを割るのにも一苦労。ようやく手にもてるくらいに重たい削岩機をガンガン動かし、横からもガガガガと割っていきながらなんとか作業スペースを確保しました。この縁ブロックを残せと言われたら、降参していたかもしれません(笑)
根っこの形はこちらの木も非常にいびつになっていて、ちょっと根付くかどうか微妙な感じではありますが、何とか根付かせたいです。
これで既存樹木の取り出しが全て終わりました。掘った庭木は一旦弊社の植木畑にてお預かりし、この作業は一旦ここまでで区切りとなります。
このあと、建物の解体、敷地の造成、新しい家の建築を経て約1年越しに庭造りに入っていくことになります。
2021年03月25日
もう何年前なのでしょうか?私も舩越造園に入社して四半世紀が経つのですが、それよりも前に舩越造園が施工した袖垣根をずっと気に入ってくれていた方が、住宅を新築されるという事で、庭造りをご依頼してくださいました。
もう何と言いますか、庭屋冥利に尽きるといいますか、逆にその当時に第一線で活躍していた庭師たちと、今現在において舩越造園で活躍してくれている庭師たちとの真剣勝負という所でしょうか?それは取りも直さず、当時社長だった先代と私との勝負でもあります。
これはもう、気持ちが引き締まります。

まずは四半世紀の永きにわたって気に入ってくれていた袖垣根のリサーチです。
欠き込んだ柱の天端に屋根型を打ち付け、ヌキ板で屋根を作る。見まごう事なき、舩越造園の仕事です。黒穂(だと思うのですが判別できず・・・)の束を多用した垣根のようです。
今回も袖垣根はリクエストに入っているので、気合が入りますね。


活かしたい庭木はいくつかありましたが、このイヌマキが一番の難題になると思われます。
既に立派に成長している庭木なのですが、ブロック塀に近く根っこが塀と干渉していることが明白です。これを掘り取るのは容易ではありませんが、お施主様が「活かして欲しい」とご要望されている限り、可能性は探っていきます。
幸い、ブロック塀も取り壊し予定だったので、住宅の解体前に当社が作業できるならば、既存のブロック塀を取り壊しながら庭木を掘り取ることも可能になってきます。
削岩機で横からブロックを壊しつつ可能な限りバックホウで根っこ周辺を掘り、難易度は高いですが頑張って掘り取りたいと思います。


また、既存庭の中にも新たな庭に活かしたい庭木があり、運び出すための通路がこれまた狭くて、ここをどう通過させるか?という所にもアイディアを出していかなければいけませんね。
こちらの仕事は、ある程度の予算感と構想を伝えてあとは庭屋さん任せという仕事になりました。
「ラッキー」なんてとても思えません・・・責任重大です・・・逆に図面と見積もりを出させてもらえる方が、気持ち的に楽です。
しかし、このような「ある程度庭屋さんに任せるよ!」という仕事も当社ではじわじわ増えつつあるのも事実で、当社の仕事を信頼して庭造りを注文して頂ける、本来ならば理想に近い庭造りができる予兆は感じています。
もっとも、先ほど言ったように、そのお任せ造園の規模が大きければ大きいほど、責任の重さも大きくて一歩引きたくなるのも事実なのですが、そういう信頼に応えようという使命感もまた不思議と強くなるので、「お任せ造園」ぜひご依頼をお願いします(笑)
2020年05月08日
防草シートとは、ウッドデッキの下や庭、玄関周り、駐車場など雑草の処理が面倒な場所や、雑草が生えてほしくない場所に敷くシートです。植物が成長するためには、日光、空気、水が必要ですが、防草シートにより日光を遮断することで草が生えにくくなります。そのため、遮光率の高いもののほうが、雑草が生えにくいということになります。除草シート、雑草防止シート、砂利下シートと呼ばれることもあります。

防草シートの専門店もあれば、100円均一の店、DIYショップなど販売している場所も色々あります。また、防草シートと一口で言っても、素材も値段もさまざまです。大きな違いが構造で、大きく織布と不織布の2つがあります。
●織布とは
繊維を織り込んだシートです。価格が安いため特に広範囲に使用する場合はコストを抑えることができます。ただし、強度が弱いものが多く、耐久年数が低かったり、とがった草などは突き抜けたりしてしまうこともあります。
●不織布とは
繊維を織らずに、絡み合わせて作ったシートです。強度が高いものが多く、ある程度の厚みがあり高密度であれば、とがった草が生えるのを抑えることができます。耐久性が高いものが多いのですが、その分コストも高くなります。
防草シートには、いくつかの素材があります。ポリエステルは、コストは高いのですが耐久性も高く、熱や紫外線で劣化しにくいのが特徴です。ポリプロピレンは環境にやさしく、酸性、アルカリ性などの耐性があります。その分紫外線に弱いというデメリットがあります。ただし、変形、劣化しにくい耐候剤を合わせて作られたシートもあります。
ほかにも、シートの厚み、目の粗さ、硬さなど、さまざまな違いがあります。シートを敷く面積、上に砂利を敷くかどうか、とがった草が生える場所、駐車場用として使うなど、状況に応じて適した防草シートを選ぶ必要があります。

防草シートの耐久年数は3年から10年ほどで、長いものだと15年というものもあります。注意したいのは、敷き方で耐久年数が変わってしまうということ。個人でも敷くことは可能ですが、敷く場所が平らでない場合や、選ぶ防草シートを間違えてしまうと、早い時期にシートが破れてしまったり、防草シートの効果を発揮しきれず、隙間やシートを突き抜けて雑草が生えてきたりしてしまうこともあります。防草シートの効果を最大限に引き出し、より長く雑草が生えないようにするためには、専門家に依頼するのもひとつの手です。
上の緑色のシートの写真は、当社でいつも使っている強力タイプの防草シートです。
非常に厚く、下からの突き破りに強いほか、紫外線に常時曝露していても劣化が遅く、シートの面積当たり材料単価は他のシートに比べて高いのですが、大変重宝しています。
下のグレー色のシートは不織布ではあるのですが、上の緑色と比べると耐久性が低く、紫外線にさらすと思ったような効果が見込めないことが分かっています。こちらは価格もお手頃な事もあり、砂利敷きとセットでご提案する際などで全体の価格を抑えたい場合などに使用しています。